Xなどを見ているとなんだかWordPressがややこしいことになっている?と思う方多いと思います。私もその一人です。
本ページではページタイトルの件について、現在で私がいろいろと調べて分かったことなどを、私見を兼ねてメモとして公開しておきます。
どうして争いになったのか..
WordPressはWordPress Foundationという慈善団体が提供するOSS(オープンソースソフトウェア(Open Source Software))で、平たく言えばいろいろな人が参加してソフトを作り、それを無償で提供していくというもの。
商標登録されていてドメイン名にwordpressという文字列を使用できないなど自由に使えない部分はあるものの、基本的には個人・商用問わず自由に使うことができます。
混同されがちなのが、wordpress.comというサービスとwordpress.orgとの違いで、wordpress.comはAutomattic社という営利企業が、WordPressを利用したウェブホスティングサービス(平たく言うとWordPressを使った有料ブログサービスを提供)を行っていること。
こちらは営利企業なので、WordPressをインストールすると勝手に自動でインストールされる「Jetpack」や「Akismet」、何かの商品をサイト上で販売する時に使用するケースが多い「WooCommerce」といったプラグインなどをwordpress.org上でプラグインとして提供していて、それらに有料プランが存在し、その収益がAutomattic社に行くというビジネスモデルになっています(注:Automattic社はその他にもいろいろな有料サービスなどを提供している会社です)。
WP Engineも同様に、有名なプラグインである「Advanced Custom Fields(ACF)」などをwordpress.org上で提供し、もちろんそれにも有料版があり、さらには同じようにホスティングサービスも提供しているという会社で、私が見る限りでは特に商標の利用制限にも違反していませんし、真っ当なサービスのように感じます。
そして今回起きたWP Engineとの紛争?は、まさにこの部分を争うもので、wordpress.comが行っているWordPressに特化してウェブホスティングサービスを、WP Engineが行うことに対して、wordpress.org側が拒絶するのはおかしいというところにあります。
え?WordPressは自由に使えるのでは?と思うかも知れませんが、ここには、wordpress.comを提供するAutomatticという会社の社長と、WordPress Foundationの創設者がMatt Mullenwegという同じ人であることが事態を複雑にしているようです。
また、WordPress Foundationは慈善団体で、寄付によって運営しており、そこに対してWP Engineが十分な寄付をしていないというところも争いの中に含まれているようですが、個人的には寄付はその人の慈悲の心の対価であり、強制されるものでは決してなく、そこに言及するのはどうなの?という感があります。
過去Wixというサービスとの間でも同じような争いがありましたが、その時はWix側がプログラムそのものを詐取して(パクって)サービス展開をしているというところだったと記憶しているので、ちょっと様相は違うのかなと思います。
私見を述べれば、wordpress.comとwordpress.orgはそれぞれ独立しているはずなのに、インストールと同時に前述したプラグインが勝手に自動でインストールされているのはどうなの?という感じもします。これはプラグインをインストールする→有料版や別のサイトへ遷移させる→そこのホスティングサービスをアピールするというビジネスモデルだと思うのですがどうなんでしょうね?(これ以上の言及は避けます..)。
「Advanced Custom Fields(ACF)」はどうなる?
本ページの「Advanced Custom Fields(ACF)」リンクをクリックすると、現在は「Secure Custom Fields」という名前に代わり、作者もWP EngineではなくWordPress.orgに代わっています。
経緯については以下のページに書かれています。
これを読むと、WP Engineのホスティングサービスにいざなう?部分は削除して、機能はそのまま残したフォークプログラム(派生化プログラム)ということのようですが、個人的には他のプラグインでも有料版へ勧誘したり、中には無料版にはほとんど機能がないというちょっと悪質かな?と思うものも数多くある中、この件だけ何で特別に?という印象は強いです。
またこれについてはプラグインガイドラインに沿って行ったことだと言っていますが、「公共の安全のために、開発者の同意なしにプラグインに変更を加えること」には沿ってないのでは?とも感じます。
まあこれによってACFを今まで使用していたサイトが即座に混乱に陥ることはないのでしょうけど、言うことを聞かなければWordPress側が半ば勝手に?プラグインをフォークしてしまうことが許されるのであれば、今後同様の事案が発生する可能性があるということも考えられるので、多くのプラグイン開発者が離れてしまう可能性もあるのではないかと危惧しています。
これについて、WP Engine側は公式ページで以下のような意見を述べています。
ACF Plugin no longer available on WordPress.org
さらに詳しく知りたい方は..
今回の経緯についてさらに詳しく知りたい方は、「The Pettiest Drama in the Tech World Is Taking Place at … WordPress?」などを読んでみるといいかも知れません。
WordPressは今後どうなっていくのか?
前述したようにWordPressはOSSという性格上、ウェブ上にプログラムソースを公開した上で、たくさんの有志の方々が参加してプログラムの作成や修正、編集、問題点の改善などを行っていますから、どこかの決まったところで作られているものと比べ、廃止や停止になる確率は低いと思われます。
ただ、Automattic(wordpress.comを運営している営利団体)のある程度のスタッフが、今回の経緯に納得がいかずに退職したというニュースも出ていることから、同調してWordPressの開発に参加していたボランティアの方が離れていく可能性はあると思います。
また、WP EngineのようにAutomatticが行っているのと同じビジネスモデルまでの構築は行わないにせよ、WordPress公式サイト上で無償のプラグインを提供し、有料のアドオンや有料版を販売して収益を得ている人の中から、ひょっとしたらWP Engineに対する扱いのようにされてしまうのでは?という懸念から、積極的にプラグインの開発を行ったり、プログラム開発への参加から離れたりするケースも発生するかもしれません。
一方私も含め、WordPressを使う側からすれば、「商用・個人問わず無料で使用できるCMS」であり、「比較的簡単にコンテンツの作成ができるブロックエディターを備えている」「多数の無料テーマやプラグインが存在し、比較的簡単に必要な機能の追加ができる」「セキュリティ面を含む本体のメンテナンス、公式上で配布されているプラグインやテーマのチェックなどが行われている安心感」といったものが損なわれていくようであれば使用を控えるケースも出てくるかも知れず、さらに人気がなくなれば参加しているボランティアの方も離れていく..といった悪循環に陥る可能性もあるでしょう。
これはWordPressに限ったことではなく、OSSの宿命なのかも知れませんね。
今回の件を調べていて初めて知ったことですが、そもそもWordPressも一からプログラムが組まれたものではなく、他のブログツールのフォーク(派生化)から始まったプロジェクトのようですしね。
以前に争いのあったWixとの件のように、末端の利用者がどうなったのかを詳しく知ることもなく円満に解決され、永くWordPressが使えるようになっていてほしいと願うばかりです。


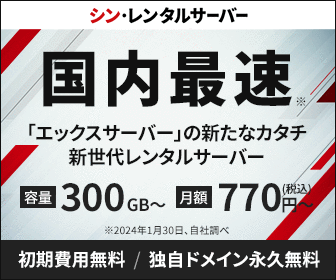








コメントを残す